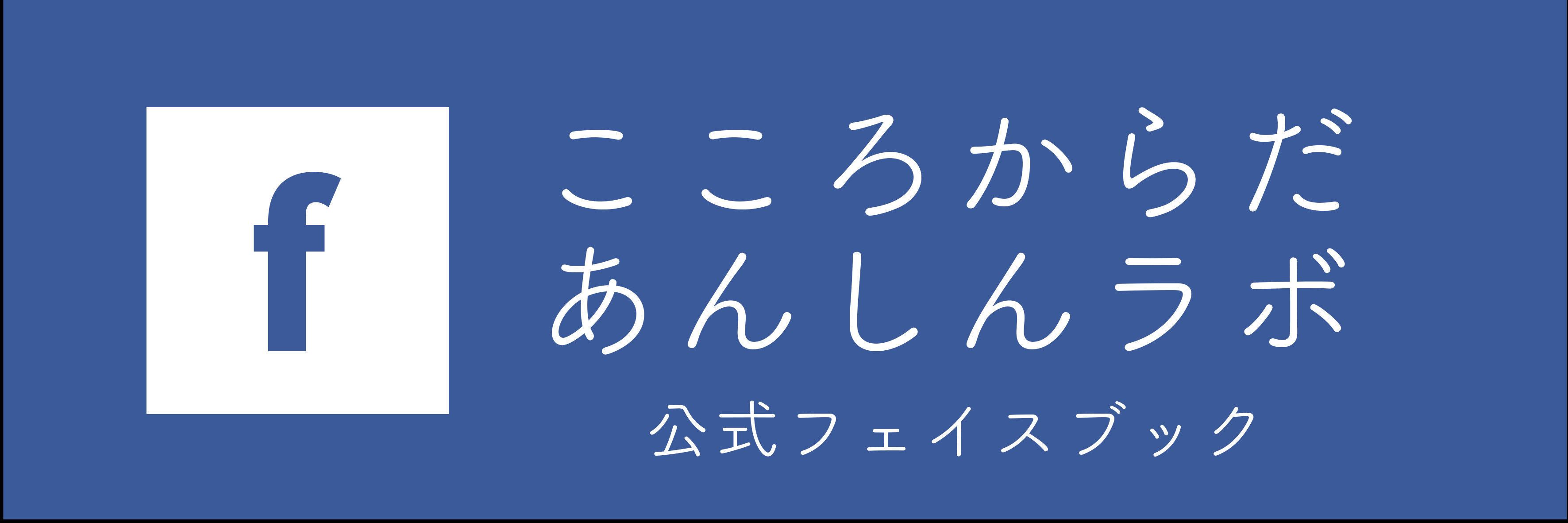みなさん、「妊娠糖尿病」という言葉を聞いたことがありますか?
自分は毎年健康診断を受けていて、糖尿病なんて言われたことは一度もないから、妊娠糖尿病も関係ない!? と思っている人も多いでしょう。
しかし、そのような人でも決して無関係ではありません。
どんな人でも診断される可能性がある「妊娠糖尿病」について、本日はお話しします。
目次
妊娠糖尿病とは?

まず、妊娠糖尿病とはどんな病気なのでしょう?
「妊娠中に初めてみつかる糖代謝異常(血糖値が高い状態)で、かついわゆる糖尿病にはまだなっていない状態」のことを指します。
妊娠糖尿病という名前なのに、「糖尿病にはまだなっていない」とは??
少しややこしいのですが、ポイントは2つです。
- 妊娠前には糖尿病ではない。妊娠前から(I・II型問わず)糖尿病と診断がついて治療中の人は、妊娠糖尿病には含まれません。
- たとえ、たまたま妊娠中にみつかったとしても、いわゆる(妊娠していない人の)「糖尿病」ほど重症なものは妊娠糖尿病には含まれません。
すなわち、妊娠糖尿病というのは、(原則)妊娠中に限定して血糖のコントロールが悪くなる、比較的軽症な糖代謝異常といえます。
妊娠糖尿病はどうやって診断するのか?

では、妊娠前に糖尿病でない人を、どうやって見つけ出す(診断する)のでしょうか?
日本の妊婦健診では毎回尿検査があり、尿に糖が出ていないかをチェックします。
また、ほとんどの施設で妊婦健診中に2回(妊娠初期、中期)血液検査があり、血糖値を測定します。
これらの検査によって、尿糖陽性が続く、あるいは血液検査で血糖値が高く出た人は、「75g糖負荷試験」という診断テストを受けることになります。
具体的には、空腹(朝ご飯抜き)の状態で甘いサイダーのような試薬を飲み、飲む直前(0分後)、60分後、120分後の3回血液を採って、血糖値を測定します。
それぞれの基準値は、
「0分後≧92mg/dL、60分後≧180mg/dL、120分後≧153mg/dL」
で、ひとつでも基準値以上だと妊娠糖尿病と診断されます。
実際に日本では、約10人に1人の妊婦さんが妊娠糖尿病と診断されるといわれており、決してまれな合併症ではないのです。
なぜ妊娠糖尿病になるのか?

妊娠中は誰でも血糖のコントロールが少し悪くなり、血糖値が高くなりやすくなります。
これは、お母さんの血液中の糖分をからだにとりこんでエネルギーにするのに必要な“インスリン”というホルモンが、妊娠中は効きにくくなっているからです。
インスリンを効きにくくすることで、赤ちゃんに送るための糖分を確保しているのです。
しかし、妊娠する前からもともとインスリンが効きにくい体質(“インスリン抵抗性が高い”といいます)の人がいます。
具体的には、年齢が高い人、体重が重い(肥満)人、そして、糖尿病の家族歴がある(糖尿病家系の)人などがあてはまります。
これらの人は、もともとインスリン抵抗性が高いところに、妊娠でさらにインスリンが効きにくくなるため、血糖値がより高くなってしまいます。
逆に、もともとインスリンの分泌が少ない体質の人もいて、そのような人も同様にインスリンの効果が足りず血糖値が高くなります(やせ体型の多い日本人では、もともとこちらのタイプが欧米と比較して多いと言われています)。
妊娠糖尿病をほうっておくと

妊娠糖尿病にかぎらず、妊娠中お母さんの血糖値が高いままだと赤ちゃんにどのような影響があるのでしょう?
非常に有名な合併症としては、巨大児(出生体重が4000g以上)があります。
赤ちゃんが大きいと、当然お産が大変になります。
赤ちゃんが産道を通ってくるのにとても時間がかかり、途中で陣痛が弱くなって、結果的に帝王切開が必要になってしまうリスクもあがります。
また、頑張って産道をおりてきたとしても、赤ちゃんの頭が出てきた後に続けて肩が出てこない“肩甲難産(けんこうなんざん)”という合併症があります。
体が出なければ赤ちゃんはとても苦しく、なんとか娩出したとしても鎖骨が折れてしまったり、腕に麻痺(動かなくなること)が出たりすることもあります。
一方で、体のサイズは大きいのですが、臓器の発達や成熟は十分でないことがあります。
肺の成長が未熟で呼吸障害(呼吸が苦しい)を起こす場合や、血糖が低くなる低血糖、ビリルビンが高くなって黄色くなる黄疸などの合併症を起こしやすいことが知られています。
加えて、血糖値が高いままだと、子宮の中の羊水が増えて羊水過多という状態になります。
羊水が増えても赤ちゃんに直接的な悪影響はありませんが、どんどん増えると子宮の許容量をこえ、陣痛がおきて早産になってしまいます。
早産で生まれてしまうと、早産児としての合併症の心配があります。
また、妊娠糖尿病のお母さんから生まれた赤ちゃんは、長期的な影響も心配です。
体重が大きく生まれた赤ちゃんは成長して成人した後、糖尿病や肥満などの生活習慣病になりやすいという報告があります。
このように、妊娠糖尿病であることに気がつかないで血糖コントロールが悪いままだと、おなかの赤ちゃんにさまざまな合併症をひきおこす可能性があるのです。
妊娠糖尿病の治療

従って、妊娠糖尿病と診断されたら、分娩まで血糖値をコントロールしていくことが必要です。治療は以下の3段階で行われます。
- 血糖測定
- 食事療法
- インスリン治療
1.血糖測定
まずは、自分の血糖値がどのように推移するのかを知ることが必要です。
ひとくちに“血糖値”といっても、食前(空腹時)血糖値と食後血糖値の2種類があります。
一日の生活の中で、朝・昼・夕のどのタイミングで血糖が高いのか、食前なのか食後なのか、それらによって治療が少しずつ変わってきます。
具体的には、各食事の直前と食後2時間の計6回の血糖測定が必要です。
これを短期間の入院(教育入院)で集中的に行って治療まで導入する方法をとっている病院もあります。
あるいは、簡易血糖測定器を用いて、自宅で自分で測定する方法(自己血糖測定、SMBGといいます)もあります。
毎日自分で測定するのは大変ですが、入院生活と自宅での生活は大きく違いますし、血糖値は妊娠経過によっても変化していくものなので、個人的にはSMBGの方がよいと思っています。
2.食事療法
通常は、血糖測定と同時に食事療法がスタートします。
食事療法といっても、流行りの糖質ダイエットをやみくもに行えばよいというものではありません。
妊婦さんは、赤ちゃんに十分な栄養を供給し、かつ産後の授乳期の準備をするために、摂取すべき必要カロリーがあります。
管理栄養士さんが、その人の妊娠週数と体格に応じて、必要なカロリー数や栄養品目にもとづいた指導をしてくれますので、それ以下に制限する必要はありません。
食事の内容だけでなく、食後の血糖が上がりやすい場合には、食事のタイミングでの摂食量を減らして間食で補う「分食」という方法で、血糖の上昇を緩やかにします。
3.インスリン治療
食事療法を行っても血糖コントロールがつかない場合には、血糖値を下げる効果のあるインスリンという薬を使います。
前に述べたように、妊娠糖尿病は、インスリンが相対的に不足して起こる病気なので、それを外から補ってあげようという発想の治療です。
インスリンは、自分で皮下に注射して投与します(お腹に注射することが多いです)。
インスリンは本来自分のからだで分泌されているホルモンですので、インスリンそのものが胎児に与える影響はほとんど心配いりません。
インスリンにも種類がたくさんあるのですが、そのなかでも妊娠中に使える、または使用経験の多い製剤を選んで使うことになります。
妊娠糖尿病では、(超)速効型と持効型の2種類のインスリンを使うことが多いです。
これは、ヒトのインスリン分泌が、基礎分泌と追加分泌とに分かれているからです。
基礎分泌とは、一日を通して血糖値を安定させるためにベースの量として分泌されるインスリンのことです。
一方、食後は一時的に血糖値が上昇するため、それに対応して基礎分泌に加えて分泌されるのが追加分泌です。
超速効型インスリンはすぐに効果を発揮して、速やかに効かなくなるため、食後の血糖上昇に対応させるように毎食前に打ちます。
持効型は24時間効果が持続するため、基礎分泌の不足分を補うために投与します(寝る前に打つことが多いです)。
単純化した説明にはなりますが、食前(空腹時)の血糖が高い場合には基礎分泌が足りていない可能性があるため持効型を増やし、食後2時間値が高い場合には追加分泌が足りていないので速効型のインスリン量を増やします。
糖尿病には、血糖降下薬といって、インスリン以外の飲み薬(内服薬)も数多くあります。
しかし、どの血糖降下薬も妊娠中には安全に使用できないため、原則はインスリンのみで治療することになります。
極端な糖質制限はNG

以上のように、妊娠糖尿病になってしまうと、毎日血糖値を測ったり、インスリンの注射をしなければならなかったりと聞くと、なるべくなりたくないなとほとんどの方が思うでしょう。
もちろん、妊娠糖尿病にはならないのが一番ですが、それを恐れるあまりに、糖質=炭水化物を極端に減らした食事(糖質ダイエット)に変えるのは、絶対にやめましょう。
あるいは、妊娠糖尿病と診断されて食事療法が始まったけれど、インスリンの注射は絶対に打ちたくないから、糖質を減らして血糖が上がらないようにしよう、というのもNGです。
妊娠中は、赤ちゃんに十分な栄養を供給しなければいけませんが、糖質は赤ちゃんの発育に必須です。
糖質を極端に制限し、体重がほとんど増えないような食生活をしていると、逆にどうなるのでしょう?
赤ちゃんはお母さんからしか栄養をもらう手段がありませんから、そのような食事をしているお母さんのお腹の中の赤ちゃんは当然栄養不足になります。
すると、十分に発育することができず、妊娠週数のわりにとても小さく(=胎児発育不全といいます)なってしまい、低出生体重児として生まれてきてしまいます。
低出生体重児は、巨大児と同様に低血糖や黄疸になりやすく、また、長期的にもやはり成人後に生活習慣病になりやすいことがわかっています。
また、お母さんの体では、炭水化物を極端に制限すると、脂肪がエネルギー源として使われてケトン体というものが産生されます。
ケトン体自体はあまり体によくなく、過剰に作られてしまうと、糖尿病性ケトアシドーシスという疾患をひきおこすリスクが高まります。
糖尿病性ケトアシドーシスは、お母さんと赤ちゃんの命にかかわるような重篤な疾患です。
このように、糖尿病と聞くと糖質をとらなければよいのかと思いがちかもしれませんが、少なくとも妊娠糖尿病においてはあてはまりませんので、注意が必要です。
食事について

では、どのような食事をこころがければよいでしょうか?
具体的なエネルギー量(カロリー)などは、個々人の体格や妊娠週数によって変わってきますので、主治医の先生や管理栄養士さんの指示に従ってください。
その上で、気を付けていただきたいポイントは、
1.食事の時間を規則正しく
生活のリズムを整えて、食事と食事の間隔が毎日バラバラにならないようにしましょう。
総カロリー数は守っていても、食事を抜いたり、食事の時間が不規則だったりすると血糖値が安定しません。
すると、血糖値が上がりやすくなったり、体重が増えやすくなったりします。
また、昼食から夕食までの時間があく(つまり夕食の時間が遅い)と、ついつい夕方くらいに間食をしてしまいがちです。
食事の時間を守ることで、余計な間食をする機会を減らせます。
2.食事の量はムラなく
1日の必要エネルギー量をだいたい三等分し、朝・昼・夕にわけて食べるようにします。
2食(朝・昼)のまとめ食いや夕食への配分過多は、やはり血糖値の乱高下をひきおこし、血糖コントロールがなかなかつかなくなってしまいます。
同様の理由で、間食はなるべく避けた方がよいのですが、もしするのであれば血糖値の上昇が緩やかになる食品がよいでしょう。
ジュースや和菓子などの糖質が多いものよりも、ヨーグルト・小魚アーモンドなどタンパク質・カルシウムを多く含むものがよいです。
これらは、妊娠中に必要な栄養素のサプリメントにもなって一石二鳥です。
3.食事の内容はバランスよく
一日の適正なエネルギーの配分は、炭水化物50-60%、タンパク質15-20%、脂質20-25%といわれています。
具体的には、日本の(典型的な)食卓では、主食(米・パン)・主菜(メインのおかず)・副菜(サラダ・お惣菜・味噌汁など)がきちんとそろうことで十分クリアできるので心配いりません。
ラーメンやカレーライスなどの一点ものは、昼食だけ・週に一度などの限られた機会であればかまいませんが、そればかりだとバランスの崩れた食生活になってしまいます。
みなさんの母子手帳には栄養バランスガイドが載っているはずですのでぜひ参考にしてください。
運動について
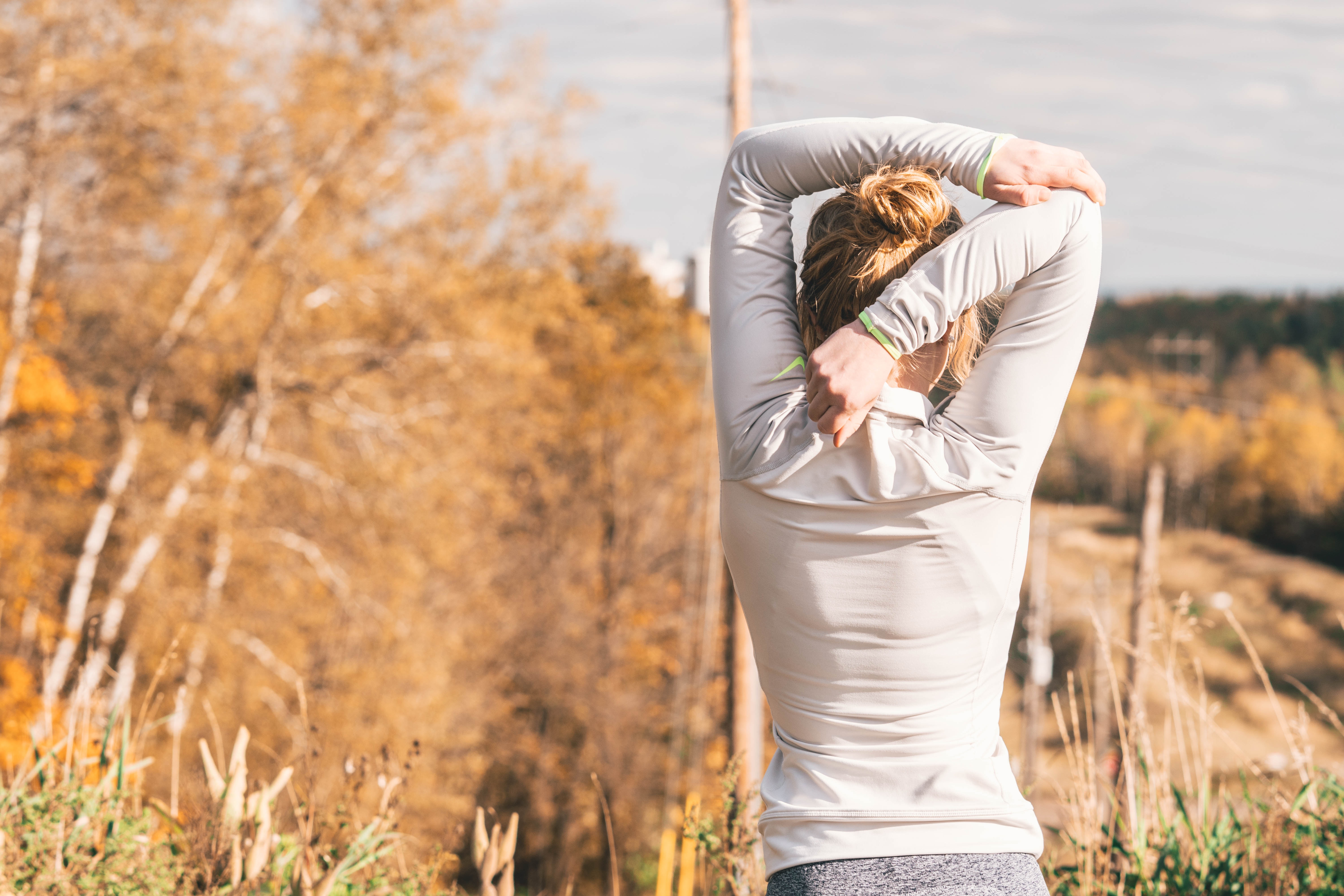
生活習慣病としての糖尿病では、運動療法は効果的でとても大切な治療法です。
しかし、妊娠糖尿病の場合にはいくつか注意が必要です。
まず、妊娠中に動きすぎてしまうと子宮の収縮が促され、場合によっては切迫早産・早産になってしまうリスクがあります。
妊婦健診で産科医から安静を指示された経験のある方もいるでしょう。
そのような人には運動療法はおすすめできません。
子宮の収縮しやすさには個人差がありますが、いずれにしろ妊娠中の運動は主治医に相談してからにしましょう。
また、妊娠中は貧血になりやすく、たちくらみや動悸を自覚する妊婦さんも多いです。
急に運動を始めてふらついてしまい、転倒でもしてしまったら大変です。
もし(主治医の許可がでて)運動療法を試したい場合には、短時間(30-60分程度)で負荷の軽い有酸素運動がおすすめです。
運動中の脈拍数が高くなりすぎない(<140回/分)ようにして、軽く汗ばむ程度の負荷がよいと思います。
ウォーキング、特に水中のウォーキングは浮力で膝や腰にも負担がかからず、全身運動になるのでよいと思います。
運動中は水分も積極的に摂取するようにしてください。
低血糖について

特にインスリンを使用しての妊娠糖尿病治療では、低血糖(血糖値<50-60mg/dL)に注意が必要です。
すぐに対応すれば問題ありませんが、適切に対応できないと重篤な症状をもたらすことがあります。
以下のような症状が出始めたら、低血糖のおそれがあります。
初期症状:発汗(冷や汗)、手足の震え、動悸など
低血糖の症状はとても個人差が大きいです。誰でも同じように症状がでるわけではないので、体調がおかしいと感じたら低血糖を疑って血糖を測定してみましょう。
↓
意識障害:脱力、眠気、集中力の低下など
対応が遅れたり、低血糖が急激におこったりすると、上記のような意識障害の症状(ぼーっとしてしまう)が出始めます。
ここで手を打たないと、意識がなくなって倒れてしまい、場合によっては後遺症を残すおそれもあります。
低血糖になったらブドウ糖(10g程度)を摂取します。
低血糖時のためのブドウ糖製剤が市販されていますし、軽度の場合には飴・氷砂糖でも対応可能だと思います。
ただし、ブドウ糖の方が、吸収が早くすぐに血糖をあげることができます。低血糖はいつどこで起こるかわからないので、すぐに摂取できるように携帯しておくことが大切です。
また、万が一、症状がひどくて自分では対処できなくなった場合に備えて、家族や職場の方にも低血糖の症状と対処法を知っておいてもらうのがよいと思います。
分娩(お産)について

妊娠糖尿病の妊婦さんでも、分娩方法は原則として経腟分娩が可能です。
帝王切開は、産科的な理由がある場合に限られます。
具体的には、分娩中に赤ちゃんの状態が悪化した場合や、分娩の進行がスムーズでなく経腟分娩が困難な場合などが挙げられます。
しかし、一般的には、妊娠糖尿病の妊婦さんでは一般妊婦さんよりも帝王切開率が高いと言われています。
これは、妊娠糖尿病になりやすい要素が、高年妊娠や肥満など、同時に、分娩の進行が遷延しやすい要素でもあることが理由のひとつでしょう。
もちろん、妊娠糖尿病のコントロールが悪くて、赤ちゃんの体重が大きければ帝王切開率も当然上がります。
また、血糖管理が不十分な場合、お母さんが妊娠高血圧症を一緒に合併する頻度も高くなると言われ、血圧が高すぎる場合にはやはり帝王切開となることが多いです。
妊娠が終わったら

妊娠糖尿病は、「妊娠中に」血糖コントロールが悪くなる疾患だと言いました。
ですので、妊娠が終了、すなわちお産が済んでしまえば、すみやかに血糖コントロールはよくなります。
というのは、インスリンの効きを悪くして妊娠糖尿病の原因となっているのは、胎盤だからです。
胎盤で作られるさまざまなホルモンによって、妊娠中はインスリンが効きにくくなっていると言われています。
分娩直前までインスリンが必要だった妊婦さんも、お産が終わったその日から、インスリンはほとんど必要なくなってしまいます。
しかしながら、妊娠が終わっても、忘れないでほしいことがあります。
それは、「妊娠糖尿病と診断されたお母さんは、将来糖尿病になるリスクが高い」ということです。
妊娠糖尿病の人が産後3-6か月に再度血糖の検査を行うと、5%が糖尿病と診断され、全体で25%(4人に1人!)になんらかの糖代謝異常がみつかるという報告があります。
また、妊娠糖尿病の妊婦さんは、正常の妊婦さんに比べて将来糖尿病になる確率が約7倍であるとも言われています。
(「なぜ妊娠糖尿病になるのか?」でも説明しましたが)妊娠糖尿病とは、もともと血糖値が高くなりやすい素因のある人が、妊娠という特別な状態になったために血糖コントロールが普段より悪くなる状態のことでした。
すなわち、妊娠糖尿病の妊婦さんが年齢を重ね、生活習慣が乱れて太ったりした場合にも、もともと素因があるのですから、当然糖尿病になりやすいということです。
しかし、糖尿病は生活習慣病といわれる通り、普段の生活習慣によって予防できる可能性が十分あります。
むしろ、妊娠して妊娠糖尿病と診断された方は、将来のリスクを予め教えてもらったようなものです。
その後の予防策が早くから立てられることを幸運と思い、ぜひ糖尿病にならないように日々の生活を見直していきましょう。
授乳について

妊娠糖尿病では妊娠が終了すれば血糖コントロールが元に戻るので、インスリン治療を授乳期まで継続しなければいけない人はまれです。
仮にインスリンを続けなければいけなくても、母乳に含まれるインスリンは赤ちゃんの腸からは吸収されませんので心配いりません。
むしろ、授乳はお母さんにもこどもにもメリットが大きいと言われています。
例えば、妊娠糖尿病だった女性では、授乳によって将来の糖尿病リスクが下がる、母乳を飲んだ子の方が肥満や糖尿病の発生が少なかった、といった報告があります。
適切な血糖値のコントロールに
妊娠糖尿病の場合、食後の高血糖が問題となりますが、
極端なカロリー制限をしてしまうと胎児発育不全を引き起こすリスクがあります。
したがって、カロリー量は極端に減らさず、食後の血糖値の急上昇を防ぐために、分食(1回あたりの食事量を少し減らしておやつを食べる)という方法があります。
この方法で、1日のトータルカロリー量を確保しつつ、食後の血糖値の急上昇を防ぐというわけです。
そうは言っても、分食による食事管理を毎日続けるのは難しいもので、
☑1食が少なめだと満足できず、つい食べ過ぎる
☑食べてもすぐにお腹が空いてしまう
☑1日に何回もバランスの良い食事を準備するのは大変
☑結局、麺類やごはんで済ませる方が手軽
などの悪循環に陥る方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方には、食前に飲むだけで糖質の吸収を抑えることができる
ノンカフェイン・無農薬 桑の葉抹茶「ゆるやか習慣」を試してはいかがでしょうか。
桑の葉に含まれる特有成分DNJは糖質(ブドウ糖)と同じ形をしており、
食前に飲むことで、胃腸はまずDNJを吸収してくれます。
その後ご飯を食べても、DNJが白米に含まれる糖質の吸収をブロックしようと働くので、
食後の血糖値の上昇がゆるやかになるのです。
このように糖質の吸収を抑える桑の葉抹茶は、妊娠糖尿病対策や糖質制限ダイエット(痩せる目的ではなく適度な体重増を目指すダイエット)にもおすすめです。 「ゆるやか習慣」詳細はこちら⇒ゆるやか習慣 公式サイト
「ゆるやか習慣」詳細はこちら⇒ゆるやか習慣 公式サイト
「ゆるやか習慣」には、ネバネバ成分で粘膜を保護する栄養素がたっぷりのレンコンパウダーも入っているので、薬が飲めない時期である妊娠中・授乳中の風邪予防にもおすすめです。
また、乳酸菌や水溶性食物繊維イヌリンも配合。
熱や酸にも強い性質の乳酸菌を使用しているので、腸までしっかりと働きかけて腸内フローラを整え、便秘解消や代謝アップのほか、先ほどのレンコンパウダーと併せてウイルスに負けない免疫力をつけるのに最適です。
水溶性食物繊維は普段の食事から十分な量を摂取するのは難しいもので、赤ちゃんに効率よく栄養を与えたい妊婦さんにはうれしい配合。さらにイヌリンは食事で摂った糖を包み込んでそのまま排出させる働きがあるので、桑の葉とダブルパワーで糖質対策ができるのです。
飲み方もとっても簡単!水やお湯に入れて混ぜるだけ。ヨーグルトや豆乳などに入れてもおいしい抹茶の味わいです。
「ゆるやか習慣」を食前のお供に、妊娠中ストレスに感じがちな食事をもっと楽しく、体重コントロールを行って行きましょう!
※既に妊娠糖尿病と診断されている方は、主治医の指示に従い適切な栄養指導・治療を受けてくださいね。